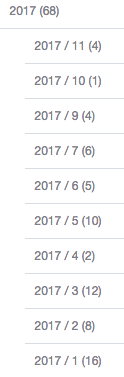町屋にできたシェアスペースをどこよりも早く紹介します
余所者がおこがましいことを言うようですが、敢えて言わせてください。
町屋の街が変わってきました。
コーヒー1杯程度の金額で一日使い放題のシェアスペースができたのです。

(公式サイトより)
2018年第一弾のエントリは、荒川区に新たに現れたこのスポット「ivyCafe neighbor&work」の紹介をしてみたいと思います。
回し者だって?ええ、回し者ですとも(嘘
恵まれた立地条件
まずは基本情報から。
アクセスがとてもよいのです。
町屋駅から歩くと、7分程度で到着します。
尾竹橋通りを北上して、ライオンズマンションを過ぎたあたりで左折。
荒川区らしい住宅地の一角に、そのスペースはあります。
蕎麦の「うじいえ」さんの真向かいになります。
自転車ヘビーユーザーの荒川区民にとって重要なポイントとして、駐輪場(予約制)も無料で使えますよ。
(ちなみにこの場所、もしや前身はこちら・・・?)
ただの作業スペースじゃない、相互交流こそが肝
このスペースは、いかなる目的をもって設定されたのか。
運営会社の公式サイトの情報の中に、開業の狙いや思いを読み取ることができます。
こちらで見てみましょう。
私たちは、みなさんの自宅の近くや通勤の途中、電車が空いてる逆方向の場所に、自宅より緊張感があり、会社よりリラックスできる空間を提供します。「ivyCafe NEIGHBOR&WORK」では、コーヒー店のように騒がしくなく、周囲の混雑や時間を気にせず、ゆっくりと自分の時間を使うことができます。
(公式サイトより、ボールドは筆者)
一つ目はつまり、読書や仕事に使うことができる作業空間ということ。
確かに2017年に「ゆいの森あらかわ」ができたことで、ノマド環境は飛躍的に向上しました。
しかし、空間のバリエーションのなさや、一極集中の弊害も感じており、滞在できる場所が街中(まちなか)に点在しているような状態を、ずっと求めていました。
まちなかの作業場所としてイメージしやすいのは、スタバやタリーズのようなWi-Fi完備のカフェがあり得ますが、なぜか区内ではそういったものは増えません。
そんな状況の中で、今回の「ivyCafe」さんのようなスポットが生まれてきたこと。
私が思うに、これこそが荒川区なりの一つの解なんだと思うのです。
さらに読み進めてみましょう。
自分の交友範囲は意外と狭いもの。会社の同僚、取引先や同業者、子供の学校や習い事関係等。私たちは、みなさんがお住まいの地域に、多様で新しいつながりが生まれる場を提供します。「ivyCafe NEIGHBOR&WORK」では、地域にお住まいの会社員、主婦、シニア、起業家、ライセンサー、クリエイター等、様々な職業や年代のみなさんが、安心してご利用いただける空間をご用意しています。
(公式サイトより、ボールドは筆者)
ここに、より深い意図が書かれています。
空間をシェアするということは、人々が物理的に短い距離で居合せるということ。
月並みですが、個がつながることで、1+1=2以上の価値を生むということに疑いの余地はありません。
そのことは私も、先日の「talk ARAKAWA」を通じて痛感しました。
こちらのスペースはどうやら、そうした相互交流を積極的に生み出していくことに狙いがあるようなのです。
相互交流のための会員専用SNSや、イベント運営などを通じてコミュニティを耕していくのだということ。
以上をまとめると、この新しい「ivyCafe」というスペースは、「作業空間」+「交流空間」ということになります。
古民家を活かした等身大の"ちょうどよい"オシャレさ
足を運んでみると、作業場所に求められる"居心地の良さ"をまずは実感することとなります。
それでは、具体的に建物の様子を見ていきましょう。(開業初日に筆者撮影)
■玄関
思わず「ただいま」と口走ってしまいそうな、上品かつ温かみのある玄関。
ちなみにシステムは現代的で、スマホアプリやPASMOでロックを解除します。(要事前登録)
■パーソナルスペース

ここでは2つの部屋を紹介しましたが、このようなパーソナルシート(予約なしで自由に使える席)が何種類もあります。
作業席ということで、パソコンや読書、勉強などを行うことができます。
言わずもがな、全席で電源とWi-Fiを利用可能です。
■ミーティングシート
個人作業以外にも、予約して使用することができるミーティングシートが2名、4名、8名向けと用意されています。
こちらは縁側のミーティングシート(〜4名)ですね。
 8名までのミーティングシートには、ディスカッションに使える黒板も設置されています。
8名までのミーティングシートには、ディスカッションに使える黒板も設置されています。
これは打ち合わせがはかどりそう。
■2階へ
驚くほど急な階段をのぼると、そこは2階です。
2階には床座タイプのパーソナルシートと、
月単位で利用することのできるプライベートシートがあります。 プライベートシートは支払いも月額なので、自分の拠点として利用することが可能です。
プライベートシートは支払いも月額なので、自分の拠点として利用することが可能です。
そんな「ivyCafe」さん、全体の間取りはこのようになっています。(いずれも公式サイトより)
■1階平面図
■1階
さて、いかがでしょう。
無料見学を受付しているほか、そもそも会員登録も無料で、利用した分だけを支払う仕組みです。
こうしたスペースは利用者が増えるほどシナジー効果を発揮していく気がするので、ぜひぜひチェックされることをオススメします。
紙芝居師の三橋とらさんがゆいの森あらかわで尾久初空襲を演じますよという話。
最近、荒川区内の至る所でこんなチラシ見かけませんか。

これ、「尾久初空襲を語り継ぐ」という催しのチラシです。
町屋でも尾久でも、はたまた南千住でも見かけるもんだから、てっきり区役所またはACC(荒川区芸術文化振興財団)あたりの主催イベントかと思っていました。
、、、マジで思っていたのですが。
主催
尾久橋町会付属「尾久初空襲を語り継ぐ会」
これを見て正直たまげました。
いち町会を母体にした催し事が、区の後援を受け、会場としてまさかゆいの森を使用するとは。。。
調べるとすぐにわかったのですが、荒川区の尾久は、第二次世界大戦で初めて本土が米軍の空襲を受けた場所なんですね。
それが1942年4月のことで、今年は被災から75年になるということでのこのイベント。
一方でイベントを紹介するウェブ媒体はないようで、検索してもちょうどよいものが引っかかりません。
そんな中、過去の取り組みと見られる記事を発見しました。
地元でも最近まで語られることがなかった「尾久初空襲」から七十五年の今年、荒川の三十代の女性が数少なくなった体験者から話を聞き集め、紙芝居にした。
(上記記事より)
なんと。
今年の4月頃に、荒川区の紙芝居師三橋とらさんが、体験者の語りを集めて作った紙芝居なのです。
これは貴重。気になります。
さらに、三橋とらさんご本人のブログも。
紙芝居の制作にかなりの苦労をされたことがわかります。
そんな三橋とらさんの紙芝居のほか、合唱と講談も含まれるこの企画は、
12月10日(日)午後1時から、ゆいの森ホールにて。
talk ARAKAWA vol.1にご協力いただいた皆様一覧【随時更新】
ありがとうございました。ありがとうございました。
もう本当に感謝なのであります。実績のない任意団体の試みにご協力いただいて。
そしてさりげなく、「これだけ巻き込めた自分頑張った!!」アピール。ふざけんなって感じですね。
でもとにかく汗をかいた。汗をかいたよ。。。。
でもなんかいろいろ難しい。難しい。
今回は、ご協力いただいた皆様をご紹介する記事です。
メディア(?)取材
絵日記ブログ「荒川区に住んでます」
もうとにかく、荒川区の有名ブロガーといえば界隈ではこの方がピカイチ。
書かれる文章のステキさとイラストの流麗さに、転居前からメロメロ。
実はもともと登壇者としてお招きしたかったのですが、とにかくこの方「荒川つま」さんとコンタクトをしてみたくて、かなり前にメールのやりとりをさせていただいていました。
また、単身者や区外からの転入者といった地域との関係を築きにくい層に、地域と関わるきっかけを提供することもねらいとしているそう。発起人のこむばさんご自身も他県からの転入者で、実行委員の方々は生粋の荒川区出身だったり、違ったバックグラウンドの方々が集まっているとのことで、どんな人にも参加しやすい雰囲気だと思います。
(上記記事より)
ありがとうございます。
田端による田端のためのwebマガジン「TABATIME(タバタイム)」
地域メディアの中でもかなり個性の強いこちら。
編集長はとある青いコンビニの店長さんです。
まだ3度しかお会いしてませんが、既に「飲み仲間」てことでいいですかね。笑
味わいのあるこの書き出しは、たぶん彼にしか書けません。
荒川区、足立区、北区など23区の中でもあまり目立たない区がありますよね
そんなことを言ってるとインターネットで叩かれそうですが、我らの田端も北区なのでお許しください。
どうもさくさく(@pirorin39)です
(上記記事より)
ありがとうございます。
文京区の地域メディア「JIBUN」
送付したプレスリリースから、素敵な記事を書いていただきました。
そしてなんと、書いてくださった方は、かつて私が入谷のrebootでまち記者講座を受講した際の講師の方。
縁というものはつながるものですね。。!
ありがとうございます。
チラシ掲出&平置き
マチヤバル三角屋
まずは私の行きつけの立ち飲み屋さん。
今年2月に開業されたばかりですが、今では連日連夜大賑わいの居心地良いお店です。
まずは荒川102の紹介記事を。
そして、私の記念すべき初入店。
食べログの記事にもさせていただきました。
こちらのお店には、なんと贅沢な場所に貼っていただくことができました!

尾竹橋通りに面してるのです。。。!
ありがとうございます。
荒川区生涯学習課
区の施設にチラシを置くということは、基本的には無理。
可能にする手段の一つとして、荒川区の後援名義を申請するというものがあるのですが、その申請にもいろいろ審査やら何やらで時間がかかる。
ですが、生涯学習課さんはもともと地域活動に従事される多くの方々と付き合いがあり、なおかつ事務局を務めるコミュニティカレッジは新たな活動者を育成する場だということもあるので、今回の「talk ARAKAWA」のような取り組みにいち早く興味を示していただくことができました。
生涯学習課は区役所本庁舎ではなく、こちらに入居されています。
ありがとうございます。
ものつくりカフェmon chouchou
SOOO dramatic!
natural cafe こひきや
あしびなぁ
MIRAI TOKYO
梅の湯
梅の湯 | 東京都荒川区の銭湯 - 東京銭湯 - TOKYO SENTO -
齋藤湯
洋菓子セキヤ
「talk ARAKAWA vol.1」についてもう少し勝手に語ってみる「我々は何者なのか?」
いろいろと書きたいネタはあるのですが、今はこれ以外モチベーションがない。
それこそ、啖呵切って書き始めた「地域コミュニティ試論」なんて、どんどん早く書き進めたいのですが。
一度プレイヤーとして走り始めてしまうと、冷静で客観的な視点なんて忘れてしまいますよね。
「talk ARAKAWA vol.1」をリリースして4日経ったけど
この企画、開催日である11月25日からちょうど3週間前である11月4日にFacebookで告知第一声を上げたわけですが。
当日はそこそこリアクションがあったものの、驚くほど反応が少ない。。。
「いいね!」はもちろんなのですが、やはり主催者としては「参加」「興味あり」の数が気になってしまいます。
毎回安定した人数が参加するイベントの凄さを改めて実感します。
ROOM810さんの「ONE HEART SHOWER」なんて最近は100名近く参加されており、もはやモンスターイベントでしょ。。。
しかし、「まあ確かになー」と思うところもあるわけです。
そもそも、どんな人たちの企画なのか?とか。
誰でも無料ですよ!みたいな公共公益系イベントではなく、やはり対価をいただく、というか、用意するものの経費を会費で回収しようとする企画なので、企画の内容と同じくらい企画主体のことも気になって然るべきですよね。
我々は何者?「talk ARAKAWA実行委員会」
そういえば「talk ARAKAWA」の企画運営を進めている集まりに、特定の名前をつけていませんでした。
でも、企画概要を示すにあたってどうしても「主催:XXXX」と書く必要が生じて。
「まあ『実行委員会』でいいか」くらいの短いやりとりで、「talk ARAKAWA実行委員会」となりました。
中高生の文化祭みたいですね。
実行委員会とは名乗るものの、別に組織の体裁はまったくなく(別にトップもいない)、ただの有志3名の集まりです。
「talk ARAKAWA」の試み(当時はまだ名前もなかったけど)はもともと2名で始まったアイデアだったのですが、その後にスキルある素敵な仲間1名に参加していただきました。
3名はそれぞれ昼間の仕事を別で抱えていますので、オンとオフの二元論で言うならば、この「talk ARAKAWA」は完全にオフ時間の取り組みということになります。
でもそれは、決して生半可な気持ちでやっているということを意味しません。
我々がゆるく共有するもの
"荒川区を盛り上げる"というテーマを掲げているものの、決して行政的な、万人に受けることをしようとしているわけではありません。
かと言って、地域活性化を食い物にしようとしているわけでもない。
あくまで自分たちにとって、面白い暮らしが手に入れたい。
そしてその”面白さ”を感じるメカニズムが、その3名の中でわりと共通していた。
それが、"街の面白い人とつながりたい”ということだったのです。
一人で街に暮らしていても街とつながるきっかけなんてない。
ましてや、一人で面白いプレイヤーと知り合うことなんて到底無理。
でも、だからこそ、それを仕組み化してしまうことには価値があると思ったのです。
自力で手に入れることがあまりにも難しいからこそ、そのプラットフォームを用意できることには間違いなく価値がある。
そしてそこで生まれる価値はソーシャルなものなので、つながりの連鎖はいずれ街を盛り上げる方向に進むでしょう。
「あれ、我々が我々自身の面白いのためにやってることって、街のためにもなるんじゃないか?」
「我々が楽しむことが、街を盛り上げること、面白くすることにつながるんじゃないか?」
ああ、もうそうなったらもう走るしかないじゃないか。
。。。はいっ。
そんな「talk ARAKAWA vol.1」は11月25日(土)に開催です。
ご関心持たれたら、以下のFacebookイベントページまで。
【告知】荒川区を盛り上げるお節介イベント「talk ARAKAWA」を開催します!
気づけば、7月の荒川区再入国以降かなり更新頻度が落ちてしまっていました。
やはり、批評家でありながらプレイヤーも演じるというのは難しいということなのでしょうか。。。
はい。というわけで。
とうとう。いよいよ。
街に仕掛けるプレイヤー見習いとして、開催までこぎつけることができました。

11月25日(土)に、「talk ARAKAWA vol.1」を開催します。 www.facebook.com
場所はこちら。

ROOM810|EVERYDAYFRIDAY | ROOM810は、建築・内装・グラフィックデザイン・メディア・企画など各分野のプロが集って起ち上げた「サービスのデザイン」を行う企業です。
Facebookページのほうは、調整を行った上での公式な情報がリリースされていますが、本エントリではもう少し勝手なことも書いてみたいと思います。笑
talk ARAKAWAとは?
企画の名前は、「talk ARAKAWA」(とーくあらかわ)としました。
これは、講演会のような一方通行的なイベントではなく、参加者相互のコミュニケーションが生まれることを企図して。
スピーチやプレゼンよりも、"トーク"という言葉には相互通行的な印象があるものと期待して。
さて、「talk ARAKAWA」では何を行うのか。
第1部 ショートスピーチ

(フリー素材より)
前半である第1部は、既に荒川区周辺エリアで活動or活躍している方々をスピーカーとしてお招きし、15〜20分程度と短めな話題提供をしていただきます。
各スピーカーが、その活動に至った経緯や思いはもちろん、街への思いや苦労話、そして踏み出したい次へのステップについてお話いただくことを想定しています。
一方のお客様として想定しているのは、かつての私と同じような層。
地域に関わった暮らしがしてみたいものの、働きかける糸口がなく、モヤモヤやウズウズを抱えている。
街のことを好きになりたいけど、家と通勤先・通学先との往復だけでは"その地域でしか味わえないこと"にアクセスすることが、どうしても難しい。
"その地域でしか味わえないこと"って何だ?それは、"ヒト"ではないか?
街の人に自己紹介をしてもらって、つなげる場を用意して、"おもしろいヒトの集まる街"としての荒川区エリアに愛着を持ってもらえると嬉しいなと思っています。
第2部 交流会

(フリー素材より)
講演を聴いただけで、何かが変わるでしょうか?答えはもちろん否です。
「明日から頑張ろうかな」といった程度の気づきはあるかもしれませんが、それすら自宅に着いた頃には忘れてしまい、結局元の日常に埋れていってしまうのではないでしょうか。
「talk ARAKAWA」はただの講演会イベントではなく、相互交流のためイベントです。
これが、お節介イベントたる由来。
それゆえ、第1部終了後、その日そこに集った方々をつなぐための、重要な第2部があるのです。
形式は、異業種交流会的な形式的アプローチと立食パーティー的な自由なアプローチで迷っていますが、とにかくこの第2部こそが本丸。
スピーカー紹介
第1回開催ということで、企画のかなりの部分が迷いながらのお試しなのですが、スピーカーさんに関しては手加減なく、私が現在知る限りのスペシャルな方々に登壇を依頼しました。
何をもってエースとするのかは難しいですが、とにかくエース級です。
下川智恵子さん(ものつくりカフェ「mon chouchou」オーナー)

(Facebookページより)
私が荒川区に転入したのは今年の7月22日なのですが、なんとほぼ同じタイミングである7月18日に開業された、南千住1丁目にある古民家ものつくりカフェ「モンシュシュ」のオーナーさんです。
下川さんはもともと荒川区南千住生まれなのですが、アパレル業界であるコドモ服メーカーで長年デザイナーとして働かれていました。
そして退職後、同じく荒川区出身のお仲間と、南千住の築120年超の民家をリノベーションし、カフェとして開業します。
それがこちら。

外観はなかなか趣ある民家そのものですが、一歩中に入ると一つ前の写真のような空間が広がっています。

季節に応じたお料理をランチとしていただくことができます。
そしてここ、ただのカフェではなく、ものつくりカフェなのです。
どういうことかと言えば、こういうことです。

ほとんど毎日というほど、手習いのワークショップが開催されており、そこには地域のママさん達が集まります。
居心地の良い空間と美味しくて安心な食事を楽しみつつ、ワークショップで習い事もすることができる。
そんな拠点を運営している下川さんに、開業に至るまでの思いや苦労、そして次に踏み出したいステップを伺います。
戸田江美さん(トダビューハイツ大家/フリーランスクリエイター)

(ご本人提供)
こちらもエース級。
たびたびこのブログでも紹介させていただいてきた、荒川区東尾久を拠点にフリーランスで活躍されているクリエイター女子です。
私が初めて遭遇した時のエピソードはこちら。
彼女はデザインやイラスト分野のクリエイターとして活躍する傍らで、地域に根ざした大家業にも力を入れています。
おばあちゃんから築40年のアパート「トダビューハイツ」 を継ぎ、一般的な不動産仲介サイトに依存せずに入居希望者を募集されています。
クリエイターさんということで、こんなステキな物件サイトを自前で作られ、なんと今やほぼ満室状態とのこと。
美大を卒業後、就職のため荒川区を一旦離れられましたが、独立して再び荒川区に戻った時に、荒川区への愛が生まれたのだと聞きます。
大家業をする上でも、"まちを気に入ってくれた人に住んで欲しい"という揺るぎないポリシーがあるそうです。
お名前で検索すると、インタビュー記事が多くヒットします。これはそのほんの一部。
20代ではじめる大家のカタチ箱庭キュレーター戸田「クリエイティブ大家さん」はじめました | 箱庭 haconiwa|女子クリエーターのためのライフスタイル作りマガジン
25才大家女子「わたしブレてます(笑)」- 物件ファンは、大家さんファン。 - 物件ファン
【ぶらり尾久散歩】パラレルキャリアな大家女子・戸田江美さんにインタビュー! | TABATIME/タバタイム
ちなみに今回、戸田さんには登壇者以外にもたくさんのお力を借りています。
お忙しい中、登壇者かつ企画者として何度も打合せさせてもらったり、デザインの力を借りたり。。。かわいいロゴできました。
兒玉匡一さん(「あらかわらいふ」発起人/代表幹事、NPO法人「東京の歴史を再発見する会」理事長)

(テレビ東京「TOKYOガルリ」HPより)
そして最後にご登壇いただくのは、荒川区の地域活動における父親のような存在。
私が転入したほぼ直後に知り合うことができ、すぐに企画理念に共感していただくことができました。
兒玉さんは千代田区で生まれ、その後豊島区で過ごされたことから、荒川区に限らず、生まれ育った東京という街そのものを深く知ってもらうために、NPO法人「東京の歴史を再発見する会」というものを平成12年に設立されています。
土日は東京各地で歴史まちあるきのガイドをされるなど、バリバリと活動されています。
一方で荒川区を舞台にした活動も多く、代表的なもののは任意団体「あらかわらいふ」です。
毎日会員の様々な写真と情報交換が飛び交っています。
他に面白いのは、「あらかわもんじゃ学研究会」の活動ですね。
区内のもんじゃ屋さんの紹介パンフを作ったりもされています。
雑誌「東京人」の先月号で取材されていました。
こうしたプラットフォームを持ちながら、さらに新しい企画や、派生プロジェクトにも取り組まれており、まさに八面六臂の活動をされています。
現在は、まさにこの「talk ARAKAWA」翌日に予定している「あらかわシャルソン」の準備に奔走されています。
このようにたくさんの顔をお持ちなので、当日はどんなアプローチでお話しいただきましょうかね。。。
talk ARAKAWAの目指すところ
「talk ARAKAWA」の狙いとして、長期的には街の魅力発信によるシティプロモーションという視点もあるのですが、まずは荒川区を中心とした"すでにお住いの方々"にとって、自身の街のスペシャル達に出会えるゆるいプラットフォームを作ることを短期的な目標としています。
なのでいまの時点での想いは、"こんな街にしたい!"という強い積極的なポリシーというよりは、どちらかと言えば"面白いことがどんどん起こる環境をつくりたい!"というもの。
町内会のような小さな単位では、学生や若年単身者など一時的な居住者が地域とつながるということは、まずありえません。
しかしその範囲をもっと広げれば、地域に関わりを持つ糸口はかなりあるのではないかという感触を、少なくとも私は経験的に持つことができました。
地域に関わり始めると、日々に刺激と安心が生まれます。
そんな仕組みやプラットフォームが街にできれば、そこで作られるネットワークは街に新しいことを起こす母体になりえます。
そんなお節介な街の変化を妄想しながらも、まずは自分がこの企画を進める中で、既に活躍されるたくさんの区内の方々と知り合えていくことが楽しくて仕方ないのです。
「talk ARAKAWA vol.1」では、そんなここまでの蓄積を皆様にお裾分けできればと思っています。
11月25日(土)14時から、場所は株式会社ROOM810さんの三階「TOKYO L.O.C.A.L LOUNGE」でお待ちしております。
参加の受付はFacebookイベントページか、talkarakawa[あっと]gmail.comまでご一報を。

地域コミュニティ試論 イントロ
地元の人と、余所者。
既存コミュニティと、流動的住民。
地域の担い手と、地域の傍観者。
もうずっと、かれこれ10年以上もそんなことを考えています。
2年未満で住まいを動き続けるような根無し草としての生活を続けている限り、おそらくそのことについて考えるのをやめられそうもありません。
そこから抜け出す手段はただ一つ、地域に根を張るということ。
終の住処とは言わずとも、”その地で生きる”という決断が必要になります。
"地域に根を張るということ"は、単に土地や家を購入することだけに限定されるものではありませんが、少なくとも通学地や勤務地へのアクセスと家計的事情のバランスだけで居住地を選んでいる段階では、到底至り得ないものではないでしょうか。
その時点で余所者は、"地元の人""既存コミュニティの一員""地域の担い手"となる資格を得ます。
難しいのは、ここで言う"資格"はやや特殊な性格を帯びており、資格を持った上で地域に入門することが求められるということです。
入門方法にはいくつかあって、まずは公園デビューからなのか、PTAに参加することなのか、町内会の組長・班長などの役職を務めることなのか、消防団に入ることなのか、他にもあるのかもしれません。
そうした試みを繰り返したところで、結果的に"地元の人""既存コミュニティの一員""地域の担い手"となるというストーリーが、まだ余所者でしかない私の推論的仮説です。
ここで私が主張したいことであり、かつ疑問なのは、"地元の人""既存コミュニティの一員""地域の担い手"になるということが、地域に根を張る前には不可能なのか?ということです。
要は、アパートで賃貸暮らしをしている学生や単身者は、地域と切り離された存在でいるほかないのか?ということ。
これまで、それに抗おうとしてきました。
町内会への参加。
地域活動への参加。
ブログによる情報発信。
地域イベントの企画。
町内会活性化戦略検討会議の発足。
既存の大きな流れへの"参加"から、次第に仕掛ける側になっていきました。
一方で、マツリズムのような、もうある程度割り切ってしまうような活動に合流したりもしました。
この試行錯誤を経て、いろいろ見えてきたことがあるので、これから何回か連載的に書いてみようと思います。
とりあえず今日は、イントロダクションということで。