町屋駅前の4つの市街地再開発事業 –「町屋銀座まちづくり? 第3回」

(2016/7/9撮影)
千代田線町屋駅を降りると、二本の高層マンション「センターまちや」「マークスタワー」がそびえ立っているのが目に付き、この街で再開発が確かに行われたということがわかります。
実はこれ以外にも町屋駅前では4箇所の再開発地区があり、それぞれに数多くの権利者が将来を構想した事実があります。
今回は町屋を調査する中で知った、そんな再開発事業について紹介しようと思います。
そもそも再開発事業とは?
まずは簡単に言葉の確認を。
正確には市街地再開発事業と言うもので、都市計画法および市街地再開発法に位置付けられた都市計画事業の一つです。
具体的には、鉄道駅前エリアに代表されるように、”本来的には土地の有効利用がされるべきなのに、実際はされていない土地”を指定して、長い期間をかけて権利者間の意思決定をします。
例えば、駅前なのに木造低層の店舗や住宅が密集している地区は、”地区のポテンシャルに反した低未利用地”と解釈され、再開発事業の候補となります。
そして事業が完了した際には、従前の権利者の持っていた権利は従後の建物の”床”に対する権利へと変換され、限られた土地面積ながら高容積の高層建築物ができるという仕組みです。
再開発事業の特徴はこの”土地→床”の権利変換。
そのほか、事業費用を賄うために従前権利者以外の床(保留床)を建物に組み込みます。
例えば、中層以上を分譲住宅として、売却益を事業費に充てるわけです。
事業のイメージは、以下の絵がわかりやすいですね。
同時に道路などの公共施設が完成していたりします。
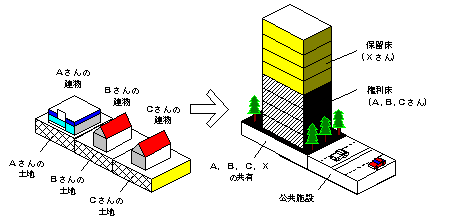
(国土交通省HPより)
実は北地区もあった?町屋駅前地区の整備構想
町屋駅前地区再開発事業の概要図が、荒川区の公式ページで出ています。

(荒川区HPより)
これを見ると、既に事業完了した再開発地区がオレンジ色で紹介されているのと同時に、”北地区”の表記が残っていることに気付きます。おや?
北地区?三井住友銀行の裏に広がるのは、密集した市街地のままでは?
そう、町屋駅前地区では、東西南北、そして中央地区の5エリアにおいて再開発事業の構想があったのです。

(『荒川区史 下巻』平成元年より)
これは、昭和57年6月の荒川区報に掲載された「町屋駅前地区整備計画試案」です。
この前年に「町屋駅周辺地区整備基本構想調査」が行われ、地域全体の課題および地区別の課題の整理結果が区より構想として発表されます。
その後、より具体的な内容を求める地元住民の声に対応する形で作成されたものがこの絵ということになります。
ここで”ブロック”と表現されている5つの街区が、再開発事業地区単位を意味します。
現在再開発事業が行われていない北地区も、この案においては2ブロックとして一づけられています。
ーしかし。
実際には、区による計画試案の発表以前から、町屋駅前地区では再開発に向けた地元の動きがありました。
そのきっかけは、昭和44年末に開通した地下鉄千代田線と、都市計画道路補助第90号線(都電通り)の拡幅事業です。
駅南側の中央地区では、地下鉄千代田線が開通(昭和四四年末)して間もないころ、工事関係業者の呼び掛けもあって、再開発に対する関心が高まり、商店主たちによって勉強会が持たれ、再開発地区の見学などを行っていた。(『荒川区史 下巻』平成元年より)
特に都電通りの拡張による補助90号線の道路工事が進むにつれ、その事業によって沿線の商店は敷地の大半を失うだけに、関心は一層高かった。(同上)
このことを自分なりに考察してみると。
既に他の公共事業によって再開発事業の機運自体は高まっていたものの、市街地再開発事業は都市計画決定という手続きで、行政主体によるオーソライズが必要とされます。
一方、”計画行政”という言葉に代表されるように、行政主体が投資や事業に関する決定を行う際、そこには計画に基づく論理性が求められます。
住民の血税の使い方に関するものなので当然なのですが、ここ町屋地区でも同様の背景がありそうですね。
行政の計画は一般に、調査→構想→計画というフローでなされます。
「都市計画決定の必要はあるけど、その上に来るべき計画がない。計画がないならば調査を行うことで構想を発表し、その後計画を策定しよう」、となるわけです。
さて、ここで各地区の再開発事業をみてみましょう。
西地区市街地再開発事業(個人施行、1987年完了) 「ウエストヒル町屋」

(2016/7/9撮影)
今現在、ファミレスのガストや居酒屋のやるき茶屋と日本海庄や、ドラッグストアの一本堂、地下にはハンバーグレストランまつもとなどが入居する低層部と、中高層部の住宅からなる薄いクリーム色の建物。
この地区が、町屋駅前地区でトップを切って完成した市街地再開発事業です。
尾竹橋通りと都電通りとの交差点の西側の一画は、町屋の中でも人通りの多い所であったが、木造の店舗や倉庫が建つだけだった。その土地所有者の一人からビル建築の申入れがあったが、区の計画を聞き、土地の有効利用を図るため、他の関係権利者を含め、区と共に協議を重ね、昭和五七年四月に西地区再開発準備研究会を発足させた。五九年一月には、市街地再開発促進区域の都市計画が決定され、同年8月には西地区市街地再開発事業の個人施行が都知事から認可された。(『荒川区史 下巻』平成元年より)
再開発事業の完了直後は従前権利者の店舗が並んでいたわけですが、
現在はスカイラークグループのガスト、大庄グループのやるき茶屋・日本海庄やによってテナントが埋められていることに寂しさを覚えてしまいます。
や、どっちも使い勝手よくて好きなんですけどね。
あと、2013年から地下1階に入居した「ハンバーグレストランまつもと」が手軽な洋食屋さんという感じで好きです。
東地区市街地再開発事業(組合施行、1988年完了) 「イーストヒル町屋」

西地区から少し離れて、京成町屋駅をくぐった先にある14階建のビル。
西地区がウエストヒルならば、東地区はイーストヒル。
1階にマクドナルド(いつの間にかセブンイレブンに。。)があるほか、大正モダニズム的なデザインの「はいから館」と称される従前権利者の店舗が1・2階に集められています。
ここでも、荒川区史から当時の雰囲気を。
町屋駅東側の東地区は、スーパーマーケット、店舗、工場・住宅・アパートなどの木造住宅が細い路地を挟んで密集混在し、防災上、問題の多い所だった。周辺には、等価交換による民間業者の高層マンションが建ち、東地区の一部にも、そのような業者による計画が早くから、持ち込まれていた。区の呼び掛けによって、昭和五八年四月、東地区再開発準備協議会が設立され、区と共に協議が重ねられた。五九年三月には、再開発準備組合が発足した。土地や家屋の権利関係が複雑で、所有者が死亡し、相続の手続きがされないままの土地があったり、また、住民にはそれぞれの事情があって、再開発の生活や営業に不安を感じる人も多く、話合いはしばしば難航した。(『荒川区史 下巻』平成元年より)
1〜2階の商店街は、若者に魅力のある街区とするため、大正モダニズムのムードを出した飲食を中心とした華やかな商店街となり、プロムナードもつくられた。(『荒川区史 下巻』平成元年より)
現在のイーストヒルを歩くと、当時の思いの詰まった低層部のデザインが今も生きていることに気づきます。
対岸の街並みと、インターロッキング状の路盤舗装と併せて、歩いて楽しいまちづくりが試みられたことが伺えます。
中央地区市街地再開発事業(組合施行、1997年完了) 「センターまちや」

千代田線町屋駅から地下で繋がっている、まさに町屋の顔とも言える再開発ビル。
前述の西地区の事業完了とほぼ同時期に再開発事業準備組合が設立しています。
この地区は、中央地区と中央第二地区(町屋ニュートーキョービル)に分かれています。
第二地区の事業では、地下鉄の出入口を京成町屋駅のすぐ近くに移設しています。
南地区市街地再開発事業(組合施行、2007年完了) 「マークスタワー」

町屋駅前地区で最も新しい最開発ビル。
住宅部分の曲面ある現代的なデザインが特徴です。
大型スーパーである赤札堂がなんといっても街のシンボルになっており、住民の日常生活の中心になっています。
町屋民だった時期、ほとんど毎日通ったなあ。。。(遠い目
北地区市街地再開発事業


さて、問題のこちらのエリア。
市街地再開発事業の候補地区であったものの、現在はまだ昔がながらの低層住宅が密集するエリアとなったままです。
この北地区では、平成17年に準備組合が解散しています。
つまり、意思決定のための協議にかなり難航した結果、都市計画決定には至らなかったということを意味します。
実はこうした地区は珍しいものではなく、権利変換によって不特定多数と共同化することとなる再開発事業の難しさがそこにあります。
さて、再開発事業についてはそんなところで。
きちんとした調査計画を作ってないと、好奇心赴くままに資料を読み漁るので、もともとのリノベーションまちづくり方面の活動が進められないのが懸念ですね。。。
とりあえず次回は、再開発事業に続いてまたもや都市計画関連ということで、町屋地区の密集市街地まちづくりについて取り上げてみようと思います。